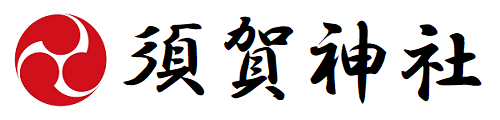古人がこの栗谷の地(現在の神奈川県多摩区栗谷1丁目から4丁目までの行政区画)を開拓し、原台、三谷、下村の3地域に24家族が定住するようになったのは、およそ安土桃山時代の頃と言い伝えられています。
その内、下村に住み着いた10家族が村落の氏神として須佐之男命(スサノオノミコト)をこの地に勧請し、奉祀したのが慶長(1596-1616)の頃となります。その社名を祭神ゆかりの須賀神社と称し、以来この地の氏神として尊崇されるようになり、祭祀が村民達に受け継がれ今日に至っています。
この間、秀吉から家康による江戸幕府時代、更に延々明治維新を経て今日に至るまで、須賀神社は五穀豊穣、家内安全、厄災消除に霊験あらたかとして崇敬されてきました。社殿は天保11年(1840年)に再建されましたが、老朽化のため昭和49年(1974年)10月1日に新社殿に建て替えられ、遷宮しました。境内地の整備に併せて、神輿・太鼓などの収蔵庫を兼ねた社務所や神楽殿も建てられました。
例祭は新緑の季節(5月頃)に開催されており、近年は神輿・太鼓の巡業も加わって、須賀神社の祭りはますます盛大になっています。